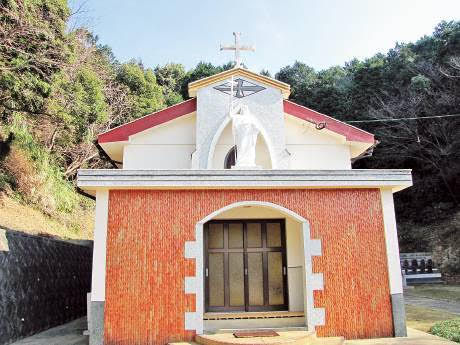万教同根・万教帰一思想を考える - 超宗教・超宗派の理念と実践
- matsuura-t

- 2023年4月15日
- 読了時間: 9分
更新日:11月25日
◯つれづれ日誌(令和5年4月12日)-万教同根・万教帰一思想を考えるー超宗教・超教派の理念と実践
すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内にいます、すべてのものの父なる神は一つである。(エペソ4.6)
前回、生長の家の三大理念の一つに「万教帰一」という考え方があるということを述べましたが、谷口雅春の古巣である大本教や、庭野日敬の立正佼成会も「万教同根」を掲げています。
谷口雅春の「万教帰一」とは、一つの根本の教えがあって、それが万の教えとして展開していることであり、宗教に違いがあるのは国や地域、民族によって服装が違うように、宗教も文化的な違いが現れているからで、大元は一つであるという思想です。
また大本教の主神は天地を創造された永遠、不変、絶対の唯一神であり(大本では大国常立大神<おおくにとこたちのおおかみ>という神名で呼んでいる)、出口王仁三郎は、本源の神の下の万教同根を唱えました。世界真光文明教団の岡田光玉も、「地球は元一つ、世界は元一つ、人類は元一つ、万教も元又一つ」と唱えました。世界の各宗教ではこの主神のことを、ゴッド、エホバ、アラー、天、ハナニムなどいろいろな名称で呼んでいます。
前回筆者は、日本の多神教の神々は、この万教同根の唯一神につなぐための橋渡しの役割を担う「途中神」だと述べましたが、同様に世界の各宗教の神も本源の神に帰一していく神であると思料致します。何故なら、そもそも全ての宗教は、神の「救済摂理」を、程度や分野や範囲や時代の違いはあっても、究極的にはそれぞれの立場で神から託された役割分担を担うために存在するものであり、摂理を担うという点において同じ目的を有すると信じるからであります。
そこで今回は、宗教の一致、即ち日本における超教派・超宗派の理念と実践について考察したいと思います。
【日本における新宗教】
先ずはじめに、天理教や大本教など、幕末から勃興した、いわゆる「新宗教」について概観することにいたします。何故なら、新宗教は、神道や仏教など、いわゆる「伝統宗教」に比して、万教同根的な開かれた発想をより積極的に思考するからに他なりません。この点、同志社大学神学部教授の小原克博氏は、「宗教の多元化と多元主義」と題する講義の中で、「新宗教の存在なくして宗教間対話は成り立たない」と指摘しています。
<新宗教の歴史と教祖>
新宗教は幕末に生まれましたが、主だった新宗教は次の通りです。創立→教祖→祭神→類型の順に記載しています。
▪️黒住教⇒1814年創立、黒住宗忠、天照大御神、神道系。
▪️天理教⇒1838年創立、中山みき、天理王命(親神様)、創唱宗教(お告げ型)・神道系。
▪️金光教⇒1859年創立、赤沢文治(金光大神)、天地金乃神(てんちかねのかみ)・生神金
光大神(いきがみこんこうだいじん)、創唱宗教・神道系。
▪️大本教⇒1892年創立、出口なお・出口王仁三郎、創造主国常立尊(=艮の金神・うしとら
のこんじん)、創唱宗教(お告げ型)・神道系。
▪️PL教団⇒1918年創立、御木徳一・御木徳近、神である大元霊(みおやおおかみ)、神道
系御嶽教系・諸宗教。
▪️霊友会⇒1923年創立、久保角太郎、釈尊、法華宗系。(霊友会の分派として、妙智会教
団・佛所護念会教団・立正佼成会がある)
▪️生長の家⇒1930年創立、谷口雅春、善一元なる唯一絶対神、悟り型創唱宗教・混合宗教
(シンクレティズム)。
▪️創価学会⇒1930年創立、牧口常三郎、日蓮・ご本尊、法華宗系。
▪️世界救世教⇒1935年創立、岡田茂吉、宇宙の創世神・大光明真神(みろくおおみか
み)、お告げ型創唱宗教・大本教分派。
▪️真如苑⇒1936年創立、伊藤真乗、釈尊、言宗系
▪️立正佼成会⇒1938年創立、庭野日敬、釈尊、法華宗系。
▪️世界真光文明教団⇒1963年創立、岡田光玉、御親元主真光大御神(みおやもとすまひか
りおほみかみ)・伊都能売大国魂大国主之大神(いずのめおおくにたまおおくにぬしのお
ほかみ)、世界救世教系。
▪️GLA(God Light Association)⇒1973年創立、高橋信次、大宇宙大神霊・仏、混合宗教
型。
▪️阿含宗⇒1978年創立、桐山靖雄、釈尊、仏教系。
▪️幸福の科学⇒1986年創立、大川隆法、エルカンターレ、混合宗教型。
以上が主な新宗教ですが、キリスト教系新宗教としては、「ものみの塔」や「日本統一教会」(1959年創立)があります。
新宗教は、時代が変化する時に勃興しています。第一次ブームは幕末維新期で、黒住教(1814)、天理教(1838)、金光教(1859)が生まれ、第二次ブームが明治末期で大本教(1892)、霊友会(1923)などで、第三次ブームが戦後期で、創価学会や立正佼成会が成長しました。また、20世紀後半に勃興した桐山靖雄の阿含宗、高橋信次のGLA、大川隆法の幸福の科学などを「新・新宗教」と呼ぶこともあります。
<新宗教の特徴>
新宗教には、神道系、仏教系、キリスト教系、創唱系、混合系など色々ありますが、その特徴として、教祖に強烈な宗教体験(神体験)があり神憑り的な「カリスマ性」があること、病気治しなど貧病争からの脱却を活用して布教に積極性があること、宗教混合的要素(シンクレティズム)があり宗教間対話など他宗教に開かれた姿勢を持っていること、などが挙げられます。
キリスト教では、16世紀の宗教改革で伝統的なカトリックと異なるプロテスタントが生まれましたが、日本の新宗教は既成の伝統宗教(仏教・神道)に対してプロテスタント的な性格と役割を持っていると言えなくもありません。概ね 新宗教は開かれた考え方を持ち、キリスト教、UCを含む、超宗教・超宗派運動の推進力になり得る宗教であると思料するものです。実際新宗教は、1651年、新宗教の超宗派連合組織である「新日本宗教団体連合会」(新宗連、2012年公益財団法人、初代理事長御木徳近、57団体加盟)を立ち上げています。
【宗教間対話の神学】
この際、全ての宗教は「神の救済摂理を担う器である」との基本的認識のもとに、異なる宗教同士をどのように関係付けるか、即ち宗教間の対話と一致の道筋を考えて見たいと思います。いわば「宗教間対話の神学」であります。
前記の小原克博氏は、宗教間の対話を進めるに当たって、宗教の基本的スタンスに3つの類型(タイプ)があると指摘されました。即ち、排他主義、包括主義、多元主義であります。
「排他主義」とは、文字通り、自宗教以外に救いはないという考え方です。使徒行伝12章12節に「この人(イエス)による以外に救はない。わたしたちを救いうる名は、これを別にしては、天下のだれにも与えられていないからである」とある通りです。創価学会では、日蓮があらわした南無妙法蓮華経の文字曼荼羅を御本尊として絶対視し、御本尊以外に成仏はないとしています。
また「包括主義」とは、自宗教が最も優れた教えであるが、他宗教にも救いの可能性があるとし、その意義を認めるものです。カトリックは1962年からの「第2バチカン公会議」で、他宗派・他宗教を否定せず対話の方針を打ち出しました。即ちそれまで掲げていた「キリスト教(教会)の外に救いなし」の文言は放棄され、現在は公式に包括主義の立場に立って他宗教との対話を行っており、カトリックの成熟を象徴しています。
また1948年に設立されたプロテスタントを中心とした「世界教会会議」(WCC)もエキュメニカル運動(教会一致運動)を採用しました。そしてこれらは「神の恵みの普遍性」という神学理念から導かれます。但し、保守的なキリスト教福音派では、エキュメニカル運動に対して、無節操な混合主義に陥るとして懐疑的態度を取っています。つまり、ファンダメンタル(原理主義)的な純粋性を保持しようとする姿勢であり、これを排他主義としていちがいに排斥できないことは確かです。
第三の「多元主義」ですが、各主教には固有の救いがあることを認め、全ての宗教は対等関係にあるとする神中心主義の考え方であります。それぞれの宗教には皆独自の固有の教えがありますが、それらの独自性は排他的な形で優越性や普遍性を主張すべきではなく、宗教の平等原則を重視するというものです。
イギリスのキリスト教哲学者ジョン・ヒックは宗教多元論の主唱者ですが、キリスト中心主義から神を中心とし、唯一の神のまわりをキリスト教を含めた諸宗教がまわる「神中心主義」を唱え、従来のキリスト教からの大転換を計りました。「すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内にいます、すべてのものの父なる神は一つである。(エペソ4.6)とある通りです。正に出口王仁三郎や谷口雅春が唱える万教同根・万教帰一の思想は神中心主義と言えるでしょう。
では以上の議論を踏まえた上で、これからの宗教間対話は、どのような理念と姿勢で取り組むべきなのでしょうか。端的に言えば、「神の恵みの普遍性」(万人救済思想)の理念のもとに、宗教的包括主義を加味した多元主義、即ち、宗教にはそれぞれの役割があるとの思想と、神のみ旨の同労者としての選民的意識を共有することだと思料いたします。
【超宗教ムーブメント】
前述したように、そもそも全ての宗教は、神の救済摂理をある段階とある分野で担うもので、時・程度・範囲・役割が違うだけで、「神の創造理想を担う」という点では共通の役割と目標を持っていると信じるものです。そしてキリスト教では、教派を超えた結束を目指し、キリスト教の教会一致を掲げる「エキュメニカル運動」が提唱されました。これはまた、広くはキリスト教相互のみならず、より幅広くキリスト教を含む諸宗教間の対話と協力を目指す運動のことを指す場合もあります。
さてUC創始者は、その生涯の活動の中で、キリスト教を中心とした超宗教・超宗派運動は、最も力を入れられた分野であり、エネルギーと時間と金銭を惜しみなく注がれました。宗教の和合一致、とりわけキリスト教の和合一致に心血を注がれましたが、これはUCだけでなく全ての宗教の夢であります。それは、創始者自身が、誰よりも真正のキリスト者であり、UC創始者である前に純然たる宗教者であったからに他なりません。
UCは、1981年には、神様会議、国際クリスチャン教授協会(ICPA)、国際基督教学生連合会((ICSA)を立ち上げ、1985年、世界宗教議会、1991年、世界平和宗教連合(IRFWP)、1999年、世界平和超宗教超国家連合(IIFWP)、2000年、米国聖職者指導者会議(ACLA)、そして2019年には世界聖職者指導者協議会(WCLA)が創設されました。その間、1991年には神学者グループによる「世界経典」が編纂されています。

このように、UCほど宗教の一致に尽力してきた宗教はなく、これは、父母なる神の下に、人類一家族の理想を掲げているからに他なりません。そこで筆者は、先ず神様会議を再生復活して「令和神様懇談会」を立ち上げること、そして「世界経典」を拡充して「新世界経典」を編纂することを提案いたします。
以上、新宗教とその位置付け、宗教間対話の理念と方案、UCの超教派・超宗派への取り組みについて述べました。(了)
牧師・宣教師 吉田宏