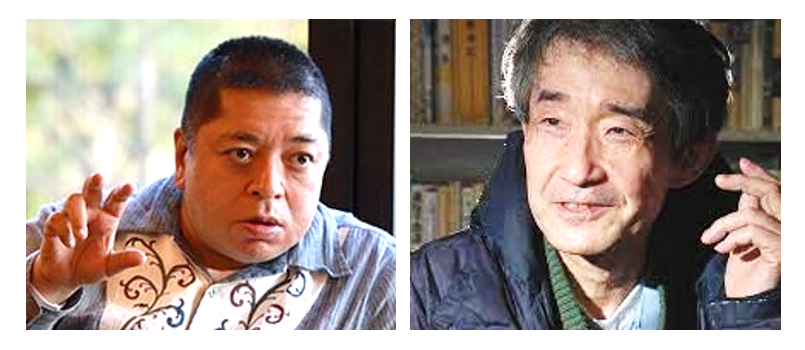新年のメッセージ - 巳年は「復活と再生」の年
- matsuura-t

- 2025年1月4日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年1月29日
◯徒然日誌(令和7年1月1日) 新年のメッセージ - 巳年は「復活と再生」の年
わたしたちは、その死にあずかるバプテスマによって、彼と共に葬られたのである。それは、キリストが父の栄光によって、死人の中からよみがえらされたように、わたしたちもまた、新しいいのちに生きるためである。(ローマ6.4)
新年明けましておめでとうございます。
さて、今年は巳年(みどし)。十二支は、12種類の動物を漢字に当てはめたもので「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」から成り立っており、巳年は、十二支の6番目にあたる。
巳は蛇を象徴し、蛇は旧約聖書では、人間に原罪をもたらした邪悪の権化とみなされ、エデンの園でエバを誘惑し、人類を罪に陥れた悪の象徴として登場する。(創世記3.1~7)
一方、「青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた」(申命記21.9)とあり、また「蛇のように賢く」(マタイ10.16)とある通り、神の使いとして再生と知恵の象徴でもある。脱皮を繰り返すことから、「死と再生の象徴」とされ、蛇を御神体として崇めている神社もある。(品川蛇窪神社)
即ち、巳年は、脱皮を繰り返して成長するヘビのイメージから、生命力や再生のシンボルとされている。従って、本年は巳年にあやかって、古い自分が死んで、新しい自分が復活し再生される「復活と再生の年」と位置付けたい。「わたしたちは彼と共に葬られたのである。それは、キリストが死人の中からよみがえらされたように、わたしたちもまた、新しいいのちに生きるためである。(ローマ6.4)とある通りである。

【死と復活】
キリストの死(十字架)と甦りはキリスト教教理の根本であり、これは贖罪と復活という二つの言葉に象徴される。使徒信条の最後のフレーズは「罪の赦し、からだのよみがえり、永遠の生命」、即ち「復活」について記されている。
今まで筆者は、「唯一神思想」、「メシア思想」、「贖罪思想」を聖書の三大思想と位置付け、この三大思想を徒然日誌で論評した(令和6年10月16日-唯一神思想、令和6年10月23日-メシア思想、令和6年12月18日-贖罪思想)。しかしキリスト教では、復活思想は贖罪思想に勝るとも劣らない意義を有しており、今回は、信仰の目的とも言うべき重要な復活の意味を、もう一度考えたい。
<キリスト教の教理は復活の教理>
文鮮明先生は、復活の意義について次のように言われている。
「本来、キリスト教の教理は、十字架ではなく復活の教理である。イエス様が復活することによって救いが成立したのであって、死ぬことによって成立したのではない。亡くなって三日後に復活されたイエス様の復活の権能によって救いを受けるのである。復活後の40日期間の基盤の上に、初めて新たな第二イスラエル、即ちユダヤ教に代わる新しいキリスト教が出発した」(『イエス様の生涯と愛』光言社P275~276)
このように、キリスト教の教理は「復活の教理」であり、新約聖書は復活の書と言ってもいい。そしてキリスト教の起源は、使徒行伝2章1節から4節の、いわゆるペンテコステと呼ばれる聖霊降臨にあると言われている。ペンテコステは、聖霊降臨と呼ばれ、イエスの復活・昇天後、集まって祈っていた120人の信徒たちの上に、神からの聖霊が降ったという出来事のことである。ユダヤ教では初穂の祭りから50日後の日曜日で「7週の祭り」(五旬祭-シャブオット)と呼ばれている。
120人門徒が一つとなって祈った時、4000年間天地の間で遮っていた死亡の圏が打ち破られ、聖霊が地上に臨むようになったのである。120人門徒の一貫した心、誠意、供え物の精神によって、聖霊の役事が出発した。イエス様は真の父、聖霊は母(新婦の霊)。この霊的な父と母の愛を受けてこそ、霊的に重生され、贖罪の恩恵を受ける。子女は父母の愛がなくては生まれることはできないからである。私たちが罪を委ねれば、聖霊とイエス・キリストが引き受けられ、その後神から清算を受けるのである。(『イエス様の生涯と愛』P277~P282)
イエス・キリストの墓は、イエスが埋葬された後に復活したと信じられている墳墓で、伝統によれば、キリストの墓の場所は、正教会・カトリック教会などが共同管理するエルサレムの「聖墳墓教会」、あるいは聖公会などが管理する旧城壁外にある「園の墓」と言われている。しかしこのどちらにもキリストの遺骸は無く、死後復活したと信じられている。イザヤ書には「彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった」(イザヤ53.9)とある。
<復活は死が前提となった言葉>
ところで、復活とは、再び活きるという意味であり、再び活きるというのは、死んだからである。つまり、復活は死が前提となった言葉であり、死と復活は表裏一体である。従って、復活するためには、一度死ななければならない。あるいは文先生の興南監獄路程のように、死よりも過酷な境地を通過しながら、生きて甦らなければならない。真に復活した人とは、真に死んだ人であり、堕落人間の最大の希望は復活にある。そしてアブラハムとイサクもモリヤの祭壇で一度死に、そして復活した。
筆者は、65才から3年間、まさに死ぬような地獄を余儀なくされたが、この地獄を通過して初めて、復活という意味が実感として理解できた。この顛末については、「徒然日誌(令和6年7月31日) 思想遍歴ー何故、聖書の研究に至ったのか」に詳述しているので、時間のある時読んで欲しい。
【検証ーイエス・キリストの復活】
ところで、「福音の三要素」とは、a.キリストは、私たちの罪のために死なれたこと、b.墓に葬られたこと、c.3日目によみがえられたこと、の三要素と言われており、この3つを信仰告白することがクリスチャンの証である。つまり、救いの条件はイエス・キリストの「十字架・埋葬・復活」の三要素であり、埋葬はその一つに挙げられている。
「わたしが最も大事なこととしてあなたがたに伝えたのは、キリストが、わたしたちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、三日目によみがえったことである」(1コリント15.3~5)
ではイエス様が死んだのち、黄泉にくだってみ言を伝えながら三日間苦痛を受けたという事実はどういう意味だろうか。それは、地獄のような最もどん底の境地に行って自ら苦痛とサタンの試練を受け、そのどん底から蘇りの道を開拓されたという意味であり、ここに「霊的復活の勝利的起源」がある。(『イエス様の生涯と愛』P268)
<イエス・キリストの復活>
既に述べた通り、キリスト教において、十字架の贖罪と復活は、二大キーワードであり、とりわけ復活は霊的勝利の証であり、キリスト教の出発点になる最も重要な概念である。
つまり、イエスの復活がなければキリスト教はなかったのである。キリスト教は十字架から始まったのではなく、復活から始まったのであり、キリスト教の祝日で「イースター」(復活祭)が最も重視されている所以である。とりわけギリシャ正教では復活を重視し、ロシア思想史をライフワークとする宗教学者の田口貞夫氏は、東西教会の違いや正教の特徴について、「東方正教は西のキリスト教に比べて、罪よりも救い、十字架よりも復活を重んずると」と指摘している。
ではイエスは復活することで如何なる勝利をもたらされたのだろうか。復活によってイエスは、「罪と死」を打ち砕いたと言われている。こうして復活されたキリストを信じるものは罪と死から解放されるというのである。
<キリストの復活とは肉体の復活か>
ではイエスの復活とは如何なる復活なのだろうか。伝統的なキリスト教では、十字架につけられたイエス・キリストが、眠っている者の初穂として死人の中から「肉体を伴って復活した」こと、即ち、「からだのよみがえり」が信仰されている。復活の後「墓が空になっていた」(ヨハネ20.3~8)こと、イエス自体が「骨と肉がある」(ルカ24.39)と言明していること、「弟子たちの前で食事した」(ルカ24.41)こと、新約聖書に十数ヶ所に渡って「死人の中からよみがえらせた」(使徒3.15、ローマ4.24など)と明記されていること、何よりも「使徒たちが証言している」(ヨハネ20.19~20)こと、などをその根拠としてイエスの体の復活を主張する。(ヘンリー・シーセン著『組織神学』聖書図書刊行会P553~555)
パウロは、「キリストは眠っている者の初穂として、死人の中からよみがえった」(1コリント15.20)と語り、イエスの復活を文字どおり、肉体の復活であると捉え、次のように記している。
「すなわちキリストが、わたしたちの罪のために死んだこと、 そして葬られたこと、三日目によみがえったこと、ケパ(ペテロ)に現れ、次に、十二人に現れたことである。 そののち、500人以上の兄弟たちに、同時に現れた。そののち、ヤコブに現れ、次に、すべての使徒たちに現れ、 そして最後に、いわば、月足らずに生れたようなわたしにも、現れたのである」(1コリント15.3~8)
しかし、十字架で死んで朽ちたイエスが肉体を持って蘇ることがあり得るだろうか。これは現代人の科学的理性では信じがたい事実であり、科学と理性に著しく反し、宗教と科学の統一を掲げる統一原理にも反している。(原理講論P31)
この点、自由主義神学の影響下にある教派や信徒の中には、肉体を伴ってのイエスの復活を事実として信じない者が少なからず存在している。自由主義神学に立つ解釈では、復活は歴史的事実ではなく信者の心のなかに原体験としてキリストがとどまり、その印象が強化されたことを意味しており、したがって「復活の記述はこの信仰の表現として創造せられたもの」であるという。
ドイツの自由主義神学者アドルフ・ハルナックは、弟子達はキリストの死を悲しむあまり、キリストを求め、精神状態を乱し、キリストを見たと信じるようになった。即ち「復活は錯乱した弟子達による錯覚である」と主張した。またルドルフ・カール・ブルトマンのように、「復活は歴史的事実や客観的事実ではなく神話であるが、ケリュグマ(宣教)において復活した」とする非神話化の脈絡からの説明もある。ちなみに「非神話化」とは、ブルトマンによって唱えられた、新約聖書の神話的世界像の解釈法で、新約聖書の奇跡物語は史的に通用する事実ではなく、信仰や実存のために何かを証言しようとするものであるとした。例えば「イエスが死者を復活させた」ということは「イエスは我々に生命を与える力を持っている」という証言になりえるという。このように新約聖書の記事を実存的に解釈しようとすることが非神話化である。
また台湾の李登輝元総統は、このイエスの肉体の復活だけは、最後まで信じられなかったと告白した。エホバの証人、クリスチャン・サイエンス、ユニテリアンなどは、肉体のよみがえりではなく、霊のよみがえりと考えている。
しかし前述したように、福音派など伝統的キリスト教では、イエス・キリストの肉体の復活は歴史上実際に起った歴史的事実であり、死から蘇り、変えられて「復活の体」となったと信じている。しかし、イエスは「閉まっていた戸を通り抜けた」(ヨハネ20.19)とあるように、この「変えられて復活の体になった」とはどういう体を言うのかが問題になる。
伝統的キリスト教では、復活の体とは「天上に生きるのに適した体」であるとし、「朽ちる体が朽ちない体に変化した」という。聖書には「一瞬に変えられる、死人は朽ちない者に変えられる」(1コリント5.51~52)とあるが、しかし、天上に生きるに適した体、朽ちない体とは一体どういう体なのか曖昧で明確ではない。
つまり、イエスの復活の真意を巡って議論は絶えず、神学上の大きな論点になっているのである。
神学者のジェーコブズは著書の中で、「死者の甦りは、哲学的な論証によっては、証明することも支持することもできず、啓示によってのみ支持される」(ジェーコブズ『キリスト教教義学』P559)と指摘し、復活信仰は理性ではなく信仰の領域、即ち信仰的事実とした。
<復活の新しい視点>
原理講論には、復活とは「死から命へ、サタンの主管圏に落ちた立場から、神の主管圏に復帰されていく、その過程的な現象を意味する」(講論P213)とあり、内村鑑三は再臨について、「再臨は肉体を伴う有形的再臨であって、人の救いは、霊だけではなく、霊と肉とによる救いでなければならず、霊の救済は十字架により成就しましたが、身体の救済は再臨によって成ります」と述べている(関根正雄編著『内村鑑三』)。
原理では、イエス・キリストの復活とは、あくまでも「霊的な復活、霊的に勝利されたイエスの完成された霊(霊人体)の復活」と捉え、肉体を伴っての復活ではないと主張する。イエス・キリストは、霊においては勝利されたが、肉体はサタンに奪われたからである。
そもそも死とは霊(霊人体)と肉(肉身)の分離を意味し、もともと肉体は朽ちて土に帰るように創造され、霊は霊界で永遠に生きるように創造されていると云うのである。伝道の書に「ちりは、もとのように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る」(伝道の書12.7) とある通りである。従って、十字架後、弟子たちが会ったイエスは、肉体を伴ったイエスではなく、霊的に甦られたイエスである。即ちイエスの復活の体とは、肉体を伴わない生命体級の霊人体の体としての復活である。
では、マタイ27章52節の「墓から死体がよみがえった」とは、いったい何を意味するのだろうか。それはあたかもモーセとエリヤの霊人体が、変貌山上においてイエスの前に現れたように(マタイ17.3)、旧約時代の霊人たちが、再臨復活のために地上に再臨したのを霊的に見て記録した言葉だったというのである。
ところで「最初の復活」とは何だろうか。聖書において最初の復活とはイエス・キリストの霊的復活を意味するが、再臨摂理においては、再臨主によって初めて人間が原罪を脱いで、創造本然の自我を復帰し、創造目的を完成させる復活をいうのである。従って、すべてのキリスト教信徒たちの唯一の望みは、最初の復活に参与することにあると言われている。
即ち、再臨主が降臨されたとき、最初に信じ侍って、復帰摂理路程の全体的な、また世界的な蕩減条件を立てる聖業に協助して、すべての人間に先立って原罪を脱ぎ、生霊体級の霊人体を完成し、創造目的を完成した人たちがここに参与できるようになるのというのである(原理講論P223)。聖書に表示された14万4千人こそ、再臨主が降臨されて、全体摂理遂行のために立てられる信徒の象徴的な全体数、即ち、最初の復活である(黙示録7.4、14.1)。
そして使徒信条にある「永遠の命」とは再臨主によって新生され、サタンとの関係を断ち切って完全な霊肉の復活の体を得た人間が持つ生命である。それは新生し神との関係を回復し質的な変化を遂げたものの持つ生命であり、また霊界での時空を超えた永生の命を得た生命(生霊体)でもあり、私たちの信仰の目的こそ、この「とこしえの命」である。
以上、脱皮を繰り返して再生する蛇の如く、死と再生の巳年にちなんで、再生、即ち復活の聖書的、原理的意味を再検証した。本年が皆様にとって、文字通り「復活・再生の年」となるよう祈念して、新年のメッセージとする。(了)
牧師・宣教師 吉田宏