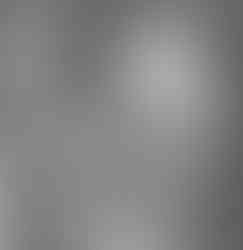イスラエルとイランの停戦合意に思う - イサクとイシマエルの葛藤と和解
- matsuura-t

- 2025年7月4日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年7月13日
◯徒然日誌(令和7年7月2日) イスラエルとイランの停戦合意に思う - イサクとイシマエルの葛藤と和解
アブラハムは高齢に達し、老人となり、年が満ちて息絶え、死んでその民に加えられた。その子イサクとイシマエルは彼をエフロンの畑にあるマクペラのほら穴に葬った。これはマムレの向かいにあり、 アブラハムがヘテの人々から、買い取った畑であって、そこにアブラハムとその妻サラが葬られた。(創世記25.8~10)
さて6月13日以来のイスラエルとイランとの紛争であるが、トランプ大統領がイスラエルとイランの停戦合意を発表し、日本時間の25日午後1時にも戦闘が終結するとした。実際、この時間が過ぎたあとも、大規模な攻撃や被害の情報はなく、この停戦合意が守られることを祈念したい。
今回の停戦合意を耳にして、筆者は、2020年8月13日、トランプ大統領の仲介で、イスラエルとアラブ首長国連邦(UAE)が結んだ「アブラハム合意」を想起した。ちなみにこの「アブラハム合意」の名称は、イサクの子孫イスラエルとイシマエルの子孫アラブの共通の父祖であるアブラハムの名に因んで名付けられた。
アブラハム合意によりUAEは、1979年のイスラエル・エジプト平和条約、1994年のイスラエル・ヨルダン平和条約に次いでイスラエルと国交正常化したアラブ世界の国で3番目となった。またアブラハム合意は、その後スーダンやモロッコがこれに倣ってイスラエルとの関係正常化に踏み出したので、この現象を総括して「アブラハム合意」と呼んでいる。
アブラハム合意には、宗教の自由、人間の尊厳と自由の尊重、相互理解と共存が唱われ、「アブラハムの宗教」(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)と全人類の平和の文化を広めるため、宗教・異文化対話の促進を努力することが唱われている。なお、このアブラハム合意の背景には、イランとの緊張の高まり、即ち、イランの核兵器開発の脅威があった。
【イサクとイシマエル】
ユダヤ人とアラブ人は、ユダヤ教とイスラム教という宗教でも対立するが、本来この両者は同じセム系民族で、一神教のアブラハムの宗教という共通点があり、共に「啓典の民」として、本来相互理解し共存すべきものである。しかし、ユダヤ人とアラブ人、ユダヤ教とイスラム教は、歴史の中で激しく戦ってきた。世界の火薬庫と言われる中東紛争がそれである。なおイラン人(ペルシャ人)は、インド・ヨーロッパ語族に属するアーリヤ系であり、ゾロアスター教に代表される独自のイランの文化を成立させたが、7世紀にイスラム教化されたので、イスラエルと敵対するアラブ側に位置付ける。
このイスラエルとアラブ・イランの紛争(中東問題)は、領土的、政治的、軍事的対立として表面化しているが、その葛藤の根源的要因はアブラハムまで遡る。即ち、旧約聖書の創世記16章から21章に記載されている、共にアブラハムの子であるイサクとイシマエルの葛藤まで遡るというのである。つまりイスラエル祖先イサクは正妻サラの子、アラブの祖先イシマエルは側妻ハガルの子で、イスラエルとアラブの対立は弟イサクと兄イシマエルの兄弟間の葛藤に根差す。
以下、創世記16章から始まるイシマエルとイサクの誕生の経緯と葛藤の顛末を見てみよう。
<イシマエルの誕生>
アブラハムの妻サラは年老いても子に恵まれず、子孫を残せないことで苦しんだ。そこで侍女のエジプトの女ハガルをアブラハムに差し出し、ハガルによって自分の子をもうけようとした。「主はわたしに子をお授けになりません。どうぞ、わたしのつかえめの所におはいりください。彼女によってわたしは子をもつことになるでしょう」(創世記16.2)とある通りである。
かくしてハガルはアブラハムの子を身籠ったが、これにより勝ち誇ったハガルは女主人のサラを見下げるようになった。 そこでサライは怒ってハガルを苦しめたので、ハガルはサライの顔を避けて荒野に逃げたという。そしてハガルは荒野にある泉のほとりで主のみ使いの声を聞いた。
「主の使は彼女に言った。あなたは女主人のもとに帰って、その手に身を任せなさい。わたしは大いにあなたの子孫を増してきれないほどに多くしましょう。あなたは、みごもっています。あなたは男の子を産むでしょう。名をイシマエルと名づけなさい。主があなたの苦しみを聞かれたのです」(創世記16.9~11)
さらに神は、「彼は野ろばのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手は彼に逆らい、彼はすべての兄弟に敵して住むでしょう」(創世記16.12)と言われて、イシマエルを独立心の強い「野ろば」と称された。
こうしてハガルはアブラムに男の子を産み、イシマエルと名づけた。このイシマエルの誕生は族長アブラハムにとってかけがえのない喜びであり安堵だったに違いない。この時アブラムは86才、サラは76才であった。ちなみにイシマエルとは「神は聞かれた」という意味であり、アラブ人の祖先となる。
<イサクの誕生>
アブラハムが99才の時、神はアブラハムに現れ、子孫と土地(カナン)の約束をされ、割礼をもって契約の証とされた(創世記17.3~8)。またサラについては「男の子が生まれる」と言われたが、アブラハムは心の中で「百歳の者にどうして子が生れよう。サラはまた九十歳にもなって、どうして産むことができようか」と笑った。しかし神は更にアブラハムに次のように言われた。(なお神は、これ以降アブラムをアブラハム、サライをサラと呼ぶように言われたが、ここでは一貫してアブラハム、サラと表記した)
「あなたの妻サラはあなたに男の子を産むでしょう。名をイサクと名づけなさい。わたしは彼と契約を立てて、後の子孫のために永遠の契約としよう。 またイシマエルについてはあなたの願いを聞いた。わたしは彼を祝福して多くの子孫を得させ、大いにそれを増すであろう。わたしは彼を大いなる国民としよう」(創世記17.19~20)
また主のみ使いもアブラハムを訪ね、「来年の春、あなたの妻サラには男の子が生れているでしょう」と言ったが、サラは「わたしは衰え、主人もまた老人であるのに、わたしに楽しみなどありえようか」(創世記18.12)と言って笑った。しかし、み使いは「主にとって不可能なことがありましょうか。来年の春、定めの時に、わたしはあなたの所に帰ってきます。そのときサラには男の子が生れているでしょう」(創世記18.14)と言ったので、サラは恐れて、これを打ち消して「笑いません」と言った。
かくしてサラは身籠り、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。 アブラハムは長く待ち望んで生れた子の名をイサクと名づけ、 8日目にその子イサクに割礼を施した(創世記21.2~4)。ちなみにイサクとは「彼は笑う」の意味である。
<イサク・イシマエルの葛藤とイシマエルの追放>
以下、創世記21章にはイサクとイシマエルの葛藤とアブラハムがイシマエルを追放する情景が描かれている。この聖書の場面にこそ、今日までのイスラエルとアラブの対立の根源的理由が秘められている。聖書は以下のように記述している。
さて、イサクは育って乳離れした(2~3才)。イサクが乳離れした日にアブラハムは盛大なふるまいを設けたが、この祝賀は事実上イサクが跡継ぎとなることの宣言もあった。この時イシマエルには自分こそアフラハムの跡継ぎであるとの自負があり、イサクをからかったという。サラはイシマエルがイサクをからかうのを見て、「このはしためとその子を追い出してください。このはしための子はわたしの子イサクと共に、世継となるべき者ではありません」(創世記21.10)とアブラハムに訴えた。
サラは、イシマエルのふるまいを見てとり(当時17才)、イサクに「長子の権利」を相続させるためには、イシマエルを追放するしかないと思ったのであろう。しかし、このことはアブラハムを非常に苦しめた。イシマエルも自分の子であったからである。
しかし神はアブラハムに、「サラがあなたに言うことはすべて聞きいれなさい。イサクに生れる者が、あなたの子孫と唱えられるからです。 しかし、はしための子もあなたの子ですから、これをも、一つの国民とします」(創世記21.12~13)と言われたのである。神の助言は、ハガル母子にとって一見ひどい仕打ちに見えるが、将来の跡継ぎを巡る争いを事前に防ぐ深謀遠慮と言えよう。神の命に従って、アブラハムは次の朝、パンと水の革袋をもたせてハガルとイシマエルを家から追い出した。神の命とは言え、我が子イシマエルの追放は、アブラハムにとって断腸の思いだったに違いない。またハガル母子にとっても、辛く悲しい別離となった。
アブラハムのイシマエルの追放 荒野のハガルとイシマエル
ハガルは去ってベエルシバの荒野にさまよったが、革袋の水が尽き、ハガルはイシマエルを木の下に寝かせ、「わたしは子供が死ぬのを見るのは忍びない」(創21.15)と言って、少し離れて彼女が子供の方に向いてすわったとき、子供は声をあげて泣いた。 神はわらべの声を聞かれ、神の使は天からハガルを呼んで、「ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神はあそこにいるわらべの声を聞かれた。わらべを取り上げてあなたの手に抱きなさい。わたしは彼を大いなる国民とするであろう」(創世記21.17~18)と言われた。
ハガルは水のある井戸を見つけ、彼女は行って革袋に水を満たし、子供に飲ませた。こうして神がその子と共におられたので、その子は成長し、荒れ野に住んで弓を射る者となった。彼がパランの荒れ野に住んでいたとき、母は彼のために妻をエジプトの国から迎えた。こうしてイシマエルはアラブの子孫となった。イシマエルの子らはハビラからエジプトの東、シュルまでの間に住んで、アシュルに及んだ。(創世記25.18)
以上がイサクとイシマエルの葛藤、及びイシマエルの追放の顛末であるが、イシマエルの誕生は人間の知恵(工作)によるものであり、イサクの誕生は天的な神の介入によるものであったと言われる。この正妻の子イサクと側妻の子イシマエルは、それぞれユダヤ人とアラブ人の子孫となるが、両者の葛藤の根源的要因は実にこの聖書の物語まで遡るのである。
【イサクとイシマエルの和解】
さて創世記25章には、アブラハムの死と葬りのことが語られている。「アブラハムの生きながらえた年は百七十五年である。アブラハムは高齢に達し、老人となり、年が満ちて息絶え、死んでその民に加えられた」(創世記25.7~8)とある。
<アフラハムの死>
アブラハムは、75才でハランを旅立ってから100年間、信仰の旅路を歩み、「選ばれた義人」、「信仰の父」、「アフラハムの宗教の祖」として、175歳の長寿を全うして息を引き取った。確かにアフラハムは信仰の父と尊称されるに相応しい生涯をまっとうしたが、しかし後々争いの原因となる種を蒔いていたのである。
即ち、アブラハムには三つの系図があり、この3つの系図はそれぞれ、アブラハムが関係を持った3人の女性を通しての、彼の子孫の3つの系図である。第一の系図はケトラという女性に関するもので、後妻(又は側妻)の系図であり、第二の系図は前記に見てきたハガルとその子イシュマエルに関するものである。このケトラとハガルの子孫は、イスラエルから見て東の方、即ち今日のアラビア半島やメソポタミア地方に住む諸民族の先祖となった。また第三の系図はアブラハムとサラの子孫に関するものである。
これらの民はイスラエルにとって、同じアブラハムを父祖とする腹違いの兄弟であるが、「アブラハムはその所有をことごとくイサクに与えた。 またそのそばめたちの子らにもアブラハムは物を与え、なお生きている間に彼らをその子イサクから離して、東の方、東の国に移らせた」(創世記25.5~6)とあるように、アブラハムはイサクを後継者に定め、イサクから腹違いの兄弟を遠ざけたのである。従って、選民としての位置はイサクが受け継ぐことになる。
このケトラとハガルの子孫は、イスラエルから見て東の方、即ち今日のアラビア半島やメソポタミア地方に住む諸民族の先祖となった。しかしここには、同じ父の腹違いの 兄弟である子供たちの間の対立、抗争が暗示されている。そこに神の霊妙な計らいがあったとは言え、この対立、争いの源は他ならぬアブラハムであり、 彼が文字通り争いの種を蒔いたと言えなくもない。
<アフラハムの葬り>
アフラハムを葬った洞穴はエフロンの畑の中にあったが、その畑は、アブラハムがヘトの人々から買い取り、妻サラを葬った所である。創世記25章には、アフラハムの葬りについて次の通り注目すべき箇所がある。
サラの埋葬・マクペラ洞穴(アブラハム、サラ、イサク、リベカ、ヤコブ、レアのお墓)
「その子イサクとイシマエルは彼をヘテびとゾハルの子エフロンの畑にあるマクペラのほら洞窟に葬った」(創世記25.9)
つまり、何十年も会わなかったイサクとイシマエルだったが、父アブラハムの死に際して再会し、共に力を合わせて父を葬ったのである。この事実は驚くべきことで、今まで恩讐関係にあった二人が父の葬儀を媒介に一つになったというのである。筆者はこの箇所を読んだ時、前述した「アブラハム合意」を想起した。2020年8月13日、イスラエルとアラブ首長国連邦(UAE)などが結んだ合意である。
同じアブラハムという父祖を持つイスラエルとアラブは、その昔、イサクとイシマエルが共に父アブラハムを葬ったマクペラの墓を想起し、恩讐を超えて和解するべきであり、このマクベラの墓こそ中東和平の精神的原点であると筆者は思料する。確かにアフラハムの後を継いだのはイサクであったが、しかし神はイシマエルにも「彼を大いなる国民とする」(創世記21.18)と大きな祝福を与えられた。そして文字通り、今やアラブ民族は大いなる民族となったのである。
以上筆者は、イスラエルとイランの停戦合意に際し、「アフラハム合意」と共に、遠くイサクとイシマエルによる「アブラハムの共同葬儀」を想起した。この共同葬儀に見られるように、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教というアブラハムの宗教が一つになる日が近からんことを祈念する。そしてこの三者の真の和解は、多くの宗教家、神学者が指摘しているように、来るべきキリストによって実現すると言われている。「キリストはわたしたちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての壁を取り除く」(エペソ2.14)とある通りである。
しかるにその雛型は、2003年5月18日、米国の牧師132名が、ユダヤ教、イスラム教の指導者と共に挙行した「エルサレム宣言」に見ることができる。即ち、文鮮明先生の主導により、三大宗教の指導者が互いに悔い改めと相互理解することを宣言し、そしてエルサレムで「十字架を埋葬する儀式」を行った。キリスト教にとって十字架は、イエス・キリストが人類を救うために犠牲となった贖罪の証だが、ユダヤ教やイスラム教にとっては憎悪と紛争のシンボルである。長年文先生は、このような複雑な背景をもつ十字架をキリスト教会から降ろすべきだと主張され、この趣旨に賛同した多くの牧師たちが、次々と教会から十字架を降ろし、そうしてエルサレムで十字架を埋葬したという。
また、2003年12月22日と23日の両日、世界平和超宗教超国家連合(IIFWP)主催で、アブラハムの宗教をはじめ約3000人の聖職者と信徒が、エルサレムで「超宗教平和行進」を行った。行事の最後には、約2万人が集まったエルサレムの独立公園で、「イエス様平和の王戴冠式」を奉呈し、イエス様の恨を解いたのである。
こうして文先生はアブラハムの宗教の和解の根本的な方案(雛型)を身をもって示されたのである。(了)
牧師・宣教師 吉田宏